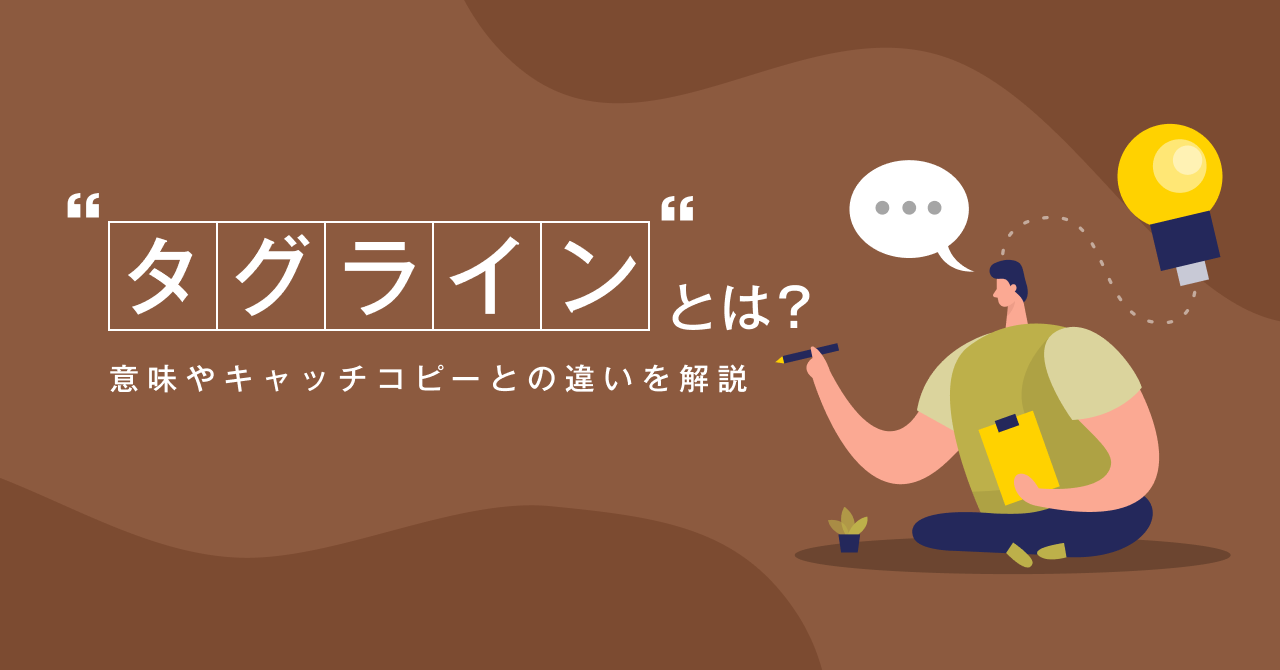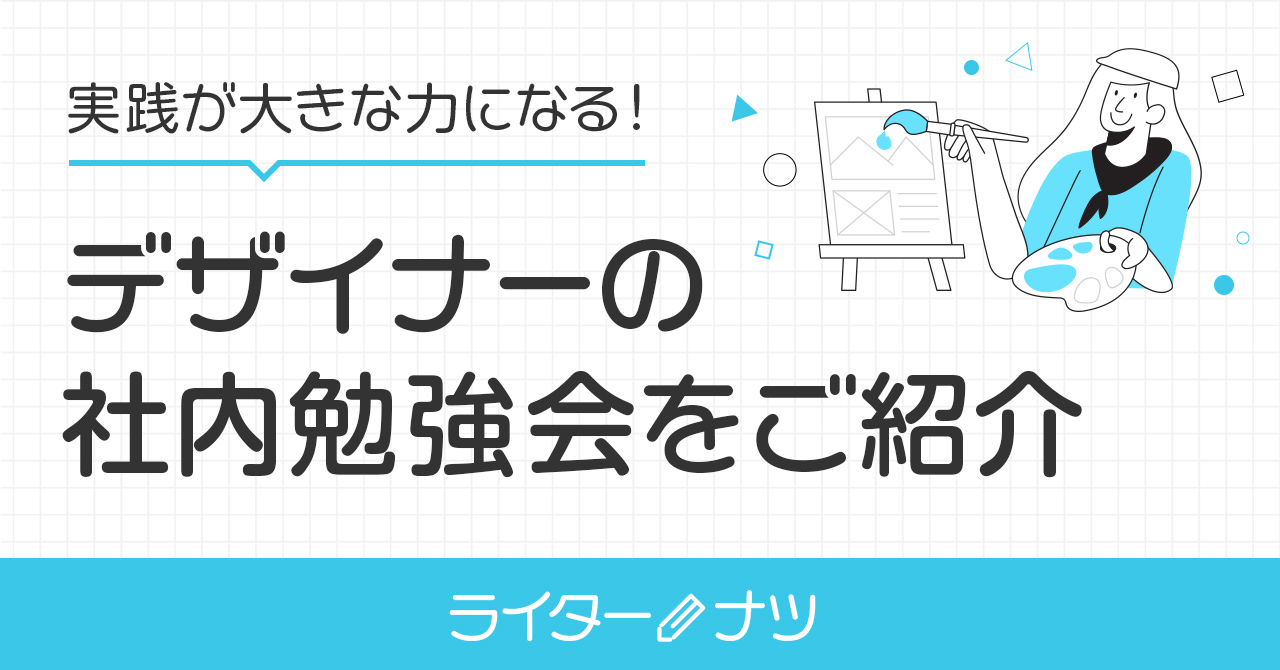デザインコンセプトの作り方、テーマとの違いや説明の例文を解説
最終更新日: 2025.03.05
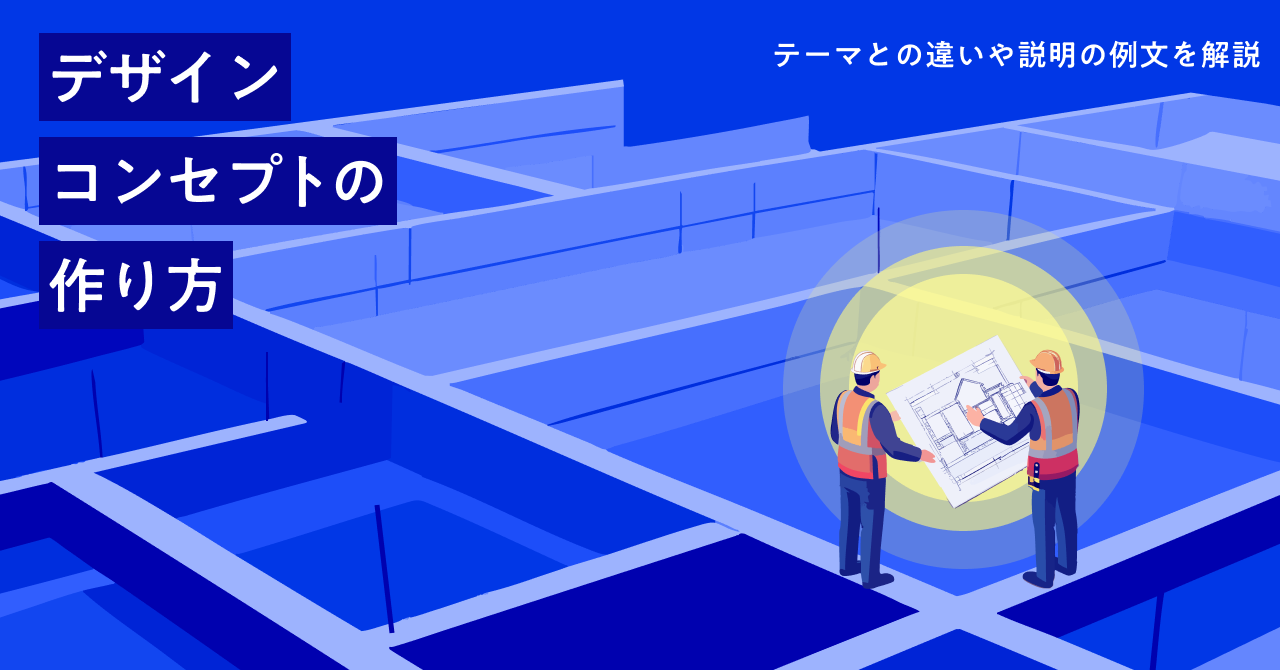
デザインコンセプトは、デザインの方向性を決める「基盤」です。
チーム内で方向性がズレないように、一貫性を持たせる、目的やゴールを明確にしておかないと、思わぬ問題に直面する可能性も。
今回は、デザインコンセプトの作り方や考え方をはじめ、テーマとの違い、提案時の説明・例文について解説していきます。
特にデザイナーさんは、「何か思っていたのと違う」と言われないように、ぜひチェックしてみてくださいね。
この記事を書いた人:カンナートブログ編集部

株式会社カンナートは「WEB制作」「システム開発」「事業化支援」を行う企業です。WEBに関わる様々なご要望にワンストップでお応えしてきたノウハウを生かし、お客様の課題を解決いたします。
ブログでは、カンナートの社員がWEB制作の過程で 「発見したこと」「便利だと思ったこと」を不定期にお届けします。
目次
デザインコンセプトとは

デザインコンセプトとは、デザインをする際にベースとなる基盤のこと。
あらかじめこの基盤を作っておくことで、複数のチームやメンバーが動く場合にも、一貫性を保ちながらデザインを進めることが可能になります。
また、デザインチーム内で多様なアイデアが出た際も、コンセプトに沿った最適な方向性が選びやすくなり、スムーズに作業を進めることができます。
ブランドのイメージを形作ると同時に、競合との差別化にも貢献する重要な要素です。
デザインコンセプトが決まらないとどうなる?
では、デザインコンセプトを設計せずに作業を進めると、何が起こるのでしょうか。
実際に、以下のような悪循環が考えられます。
- プロジェクトメンバー間で完成イメージに差が生じ、目指す方向がブレる。
- 曖昧なターゲット設定により、サイトの設計が不完全。
- クライアントが求めているものとズレたデザインが完成。
- コンセプトに沿わない、ニーズにも応えられないサイトになってしまう。
このような負の連鎖に陥ってしまい、クライアントからの信頼も失いかねません。
一度失った信頼を取り戻すことは非常に大変なので、デザインコンセプトの設計は丁寧に行うようにしましょう。
デザインコンセプトを作成するメリット

デザインコンセプトを正しく設計することには多くのメリットがあります。
ここからはデザインコンセプトを作成するメリットを説明していきます。
デザインが統一できる
デザインコンセプトを作成することで、プロジェクト全体を通して一貫したデザインを作ることができます。
色・フォント・レイアウトなどが統一されていれば、見た目や雰囲気に一貫性があり、バラバラな印象を与えません。
例えば、色に関しては具体的なカラーコードまで決めておくことで、サイト内の異なるページも統一した印象を持たせることが可能です。
このように、具体的なコンセプトがあれば、方向性のブレもなく各要素の方向性が定まります。
チーム内で認識を合わせられる
チームの全員が共通の理解を持ち、一貫した行動を取れることは、プロジェクトや業務を円滑に進めるうえで欠かせません。
特に、大きなプロジェクトでは複数のデザイナーやコーダー、ディレクターが関与するケースが多くなります。
このような状況でも、コンセプトが明確に定まっていれば、メンバー間で認識のズレが生じにくく、統一されたデザインを進めることができます。
デザイン説明時に説得力が増す
作成したデザインの意図を説明する際には、「論理的な説明と視覚的な補足」が重要です。
例えば、IT企業のロゴデザインを提案する際、単に「シンプルでカッコいいデザインにしました」と説明するだけでは、相手に十分な納得感を与えられません。
「最先端のテクノロジーを象徴するために、直線的なフォントを採用し、ミニマルなデザインに仕上げました。また、ブランドの信頼性を高めるために、知的で落ち着いた印象を与える青色を基調としています。」といったように、ただ「カッコいい」「見やすい」だけではなく、「なぜこのデザインなのか?」をより具体的にすることで、顧客に対して説明する際にも説得力を高めることが可能になります。
競合や他のデザインと差別化できる
市場には類似したデザインが数多く存在するため、デザインコンセプトを確立することは、他と差をつけるための強力な手段となります。
また、競合との差別化を図るには、「自社ならではの強み」を明確にし、それをデザインへ反映させることが重要です。
具体的な方法としては、以下のようなアプローチが考えられます。
- 競合分析を行い、共通点と差別化できるポイントを把握する
- ブランドの独自性やコンセプトを明確にする
- カラー、フォント、レイアウト、UI/UXなどのデザイン要素に反映して差をつける
- データや理論を活用し、説得力のあるデザインの根拠を示す
これらの手法を取り入れることで、他にはない独自性を持ったデザインを実現できます。
テーマとデザインコンセプトの違いとは

まず、テーマとは、デザイン全体の主題や雰囲気を決める大枠のアイデアを指します。
テーマでは、作品・ブランド・プロジェクトの「軸」となる考え方や、感覚的・抽象的なイメージが中心となります。
一方、デザインコンセプトとは、設定したテーマをどのように具体的なデザインに落とし込むかを示す指針です。
配色・フォント・レイアウト・質感・UI/UXなどの方向性を決めるといったことが必要になります。
また、デザインコンセプトには、目的やターゲットに応じた「意図」が含まれることも特徴です。
以上のことから、テーマを具体的なデザインに落とし込むための指針が「デザインコンセプト」であり、それぞれ別々の役割があります。
デザインコンセプトの決め方
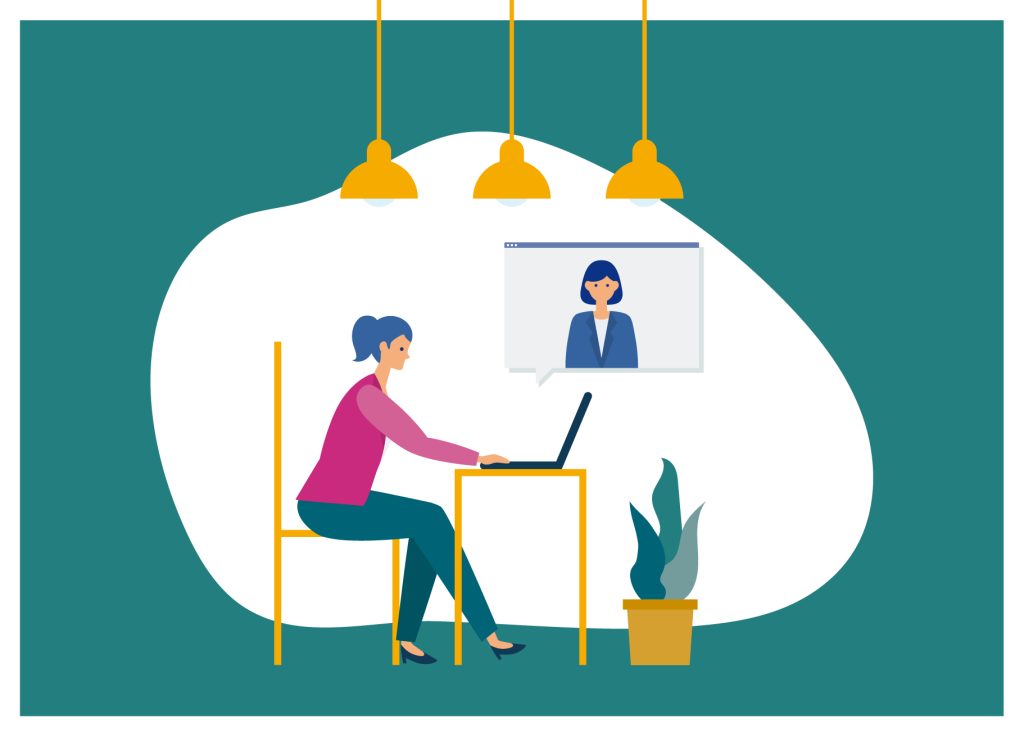
デザインコンセプトの決め方は、テーマや目的を具体的なデザインに落とし込むための重要なステップです。
ここからは、デザインコンセプトを決める際に考える必要がある要素や、その決め方について説明していきます。
5W1Hを意識して、誰に何を伝えるかを整理する
デザインコンセプトを決める際、5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)を使うと、ターゲットや目的が明確になり、説得力のあるデザインが作れます。
- Who(誰に):誰がターゲットか?
- What(何を):どんな情報・価値を伝えるか?
- When(いつ):どのタイミングで使われるか?
- Where(どこで):どの媒体・場所で使われるか?
- Why(なぜ):なぜそのデザインが必要か?
- How(どのように):デザインでどう表現するか?
これらの内容を明確にすることで、デザインの意図が説明しやすくなり、説得力が増します。
また、チーム内で共通認識を持ちやすくなることもメリットの1つです。
ペルソナを設定する
ペルソナとは、「理想的なターゲットユーザーを具体的な人物像として設定する」こと。
年齢・性別・ライフスタイル・趣味・価値観などを詳細に設定し、「この人ならどう感じるか?」を考えながらデザインを決めるのがポイントです。
上記の5W1Hをベースに、以下のように深掘りしてみましょう。
- 基本情報を決める(Who:誰?)
→ターゲットをできるだけ具体的に想定します(名前・年齢・性別・職業・居住地)。 - ライフスタイルを設定(What:何を求めている?)
→休日の過ごし方、 SNSの利用、どんなブランドが好きか、よく使うデバイス(スマホor PC or タブレット)など - 悩みやニーズを考える(Why:なぜこのデザインが必要?)
→どんな課題や悩みがあるか、どんな情報を求めているか、どんなデザインなら心に響くかなど。 - 行動パターンを設定(How:どうやって情報を得る?)
→どんなタイミングでサイトを訪れるか、どこで情報収集するか、どのデバイスで見るかなど。 - ペルソナをストーリー化してまとめる
→最後に、今までの情報を1つのストーリーにまとめると、よりリアルなターゲット像が見え、作るべきデザインが明確になります。
サービスや製品に関する情報やキーワードを洗い出す
デザインやマーケティング戦略を考える際には、「どんな情報やキーワードがあるか」を整理することが重要です。
これを行うことで、コンセプトが明確になり、デザインの方向性がブレにくくなります。
洗い出しの手順としては、以下を参考にしてみてください。
- 製品・サービスの基本情報を整理する
→まずは、サービスや製品について基本的な情報をリストアップします。何の商品・サービスか、どんな特徴・機能があるか、競合とどう違うか?(差別化ポイント)、ターゲットは誰か?(ペルソナ) - 5W1Hで深掘りする
→サービスや製品の情報を5W1H(Who, What, When, Where, Why, How)を使って整理すると、伝えたいポイントが明確になります。 - 関連するキーワードを洗い出す
→キーワードをリストアップすると、マーケティングやデザインのヒントになります。 - ビジュアルで整理(マトリクス図、マインドマップ等)
→洗い出したキーワードをカテゴリーごとに整理しまとめましょう。
コンセプトをデザインに反映する
ここまで洗い出せたら、テーマを表現するためにコンセプトに落とし込んでいきます。
- トーン(イメージ)
→「安心感」や「落ち着き」といった、サイト全体を通したテイストのことを指します。他にも、「高級感・上品さ」や「親しみやすさ・カジュアル」などもトーンに含まれます。 - 色(カラー)
→カラーは与える印象を変えるための重要な要素であり、メインカラーに加え、サブのカラーも決めておきます。例えば、IT企業であればメインカラーをブルーにして信頼性を感じさせ、サブカラーのホワイトやグレーで洗練された印象を与えることができます。 - フォント(タイポグラフィ)
→どんな種類のフォントを使うか以外にも、文字の大きさや太さも決めておくことで、統一感が高まります。例えば、可読性を重視する場合はヒラギノ角ゴ、Noto Sans、メイリオを使用するのがおすすめです。 - レイアウト(構成・余白)
→レイアウトは、情報の伝わりやすさやブランドの雰囲気に影響を与えるので、特に余白のルールは明確するのがおすすめ。例えば、視線の流れを意識し「F字型」「Z字型」のどちらを採用するのかや、余裕のあるデザインに見せるために~px以上余白を開けるのかなどは統一させるようにしましょう。 - UX/UI(ユーザー体験)
→レイアウトだけでなく、ユーザーがクリックや離脱など行動したときに、どういった動きを想定するかも重要です。例えば、ユーザーが実際にクリックしたときに軽く沈み込むエフェクトを表示するなどが該当します。
ここまで各要素を決め、最終的にコンセプトをまとめたコンセプトシートを作成すると、デザインの指針として誰が見ても一目で方向性がわかるアウトプットとなりますよ。
デザインコンセプトを説明する際の例文も紹介

弊社カンナートのデザインチームでは、実際にデザイン提案に際し、以下のようなデザイン趣意書の作成をマストとしています。
・ターゲット・課題・与件の整理
・デザインコンセプト・意図
・スタイル(カラー・フォント)
・デザイン詳細説明
ここからは、特にデザインコンセプトやスタイルを中心に、実際の提案説明を紹介していきます。
———–
■デザインコンセプト
1. 情報整理と動線配備
セクション単位で情報を整理しつつ、欲しい情報にダイレクトに遷移ができるよう動線を配備しています。
また、ユーザーの使い勝手を向上させるため、項目ごとに紐づいた受講要領はトップページからも閲覧出来るようリンクを設置しています。
今回のサイトデザインの目的として、基本的に遷移させる事が目的のためシンプルなデザインを採用しています。
2. 全体トーン
心理的な負担を和らげ、安心感を与える緑をアクセントとし、基本カラーは白・グレーを使用することで画面越しにも安心感や癒しを与えるトーンを意識して採用しています。
■カラー
白・グレーをベースにリラックスしつつ集中力を高められる青と緑をアクセントとして使用しています。
・ベースカラー(ブランドの核となるカラー)
プライマリカラー:#ffffff
セカンダリカラー:#3C3C43
・アクセントカラー(アクセントとしてポイントで使用するカラー)
#00AAB5・#1798D1・#FECB01
・ニュートラルカラー(背景色や文字、ラインのカラー)
#898989・#F5F5F5
■書体
読みやすく、認知度も高いnoto sansをベースとし、英表記も基本ゴシック系で揃えています。
また、Webフォント使用を想定しています。
・和文:Noto Sans JP
style:normal、letter spacing:5%、weight:Regular
主に日本語のテキストスタイルとして使用する。
・英文:Roboto
style:normal、letter spacing:2%、weight:bold
主に英語のテキストスタイルとして使用する。
———–
まとめ
デザインコンセプトは、デザインの根本的な方向性や価値観を表現するアイデアやテーマです。
単なる見た目を決めるだけでなく、ブランドのアイデンティティを表現し、どんな印象を与え、どんな体験を提供するかを明確にするためのものになります。
また、念入りにデザインコンセプトを決めておくことは、デザインの質向上、プロジェクトの円滑進行、最終的な成果物が結果に結びつきます。
今回の記事で紹介した決め方を参考に、より効果的なWEBサイトを作るために、丁寧なコンセプト設計を心がけてみてください。